前回のコラムでは、「いまどきのITを読み解く『サービス層モデル10階層』完全ガイド」【こちら】を紹介しました。今回は、これらの技術要素がどのように業務で活用できるのかを掘り下げていきます。
情報処理モデルの全体像
まず、人の行動(業務含む)を「情報の収集・蓄積」「情報処理(判断)」「アクション」の3段階に分けて捉えるモデルを紹介します。この3ステップは、それぞれにおいて“どの程度業務の高度化が進んでいるか”という観点でレベル分けできます。
図:情報処理モデルの4レベル分類と3ステップ
情報の収集・蓄積
- レベル1:散らかった状態(アナログ)
情報が紙の書類などで無秩序に保管されていて、探すのも一苦労。まるで「月曜から夜ふかし」に出てくる桐谷さんの部屋のような状態です(笑)。 - レベル2:整理されたアナログ情報
書類は取引先別や日付別などに分けて整理されており、必要な情報が以前より見つけやすくなっています。 - レベル3:デジタル化された情報
情報がデジタル化されてデータベースに保存されており、検索や再利用がしやすい状態です。 - レベル4:非構造データまで扱える状態
画像や音声、動画など従来扱いにくかった「非構造化データ」もデジタル化され、活用できるようになっています。
情報処理(判断)
- レベル1:勘に頼った判断
経験やデータではなく、その場の直感や雰囲気で判断している状態です。 - レベル2:経験に基づいた判断
個人の過去の経験を頼りに判断している状態で、中小企業ではよく見られます。 - レベル3:組織としての判断
社長や上司の承認(稟議)を経て判断される仕組み。スピードは落ちますが、ミスを減らせるのがメリットです。判断基準をルール化することで、安定した運用も可能になります。 - レベル4:人に頼らない自動判断
あまり重要でない日常的な判断をAIなどに任せることで、時間を節約できます。人が関わらなくても判断が可能な領域が増えてきています。
アクション
- レベル1:手順が決まっていない属人作業
作業内容が明文化されておらず、その人しかできない状態。ブラックボックス化しやすく、担当者の負担も大きくなります。 - レベル2:手順が決まっている(標準化)
誰が行っても同じようにできるようにマニュアル化された状態。担当者が変わっても対応しやすく、多能工化が進みやすくなります。 - レベル3・4:ロボットやシステムによる自動処理
定型作業を人ではなく機械が行うため、ミスやばらつきが減ります。人の体調やモチベーションにも左右されず、24時間稼働も可能です。
野球で理解する情報処理モデル
情報の収集・処理・アクションという流れを、スポーツでの意思決定に置き換えると非常にイメージしやすくなります。 たとえば、バッティング時の動きも、次のように4段階に分けて捉えることができます。
図2:野球のバッティングにおける情報処理モデルのレベル分類
このように、野球の世界もすでにレベル4の高度化が進んでおり、「どんな状況でも安定した成果(ヒット)を出す」=再現性の高いプレーが可能になってきています。
筆者も趣味でゴルフをたしなみますが、YouTubeでよく見る「てらゆー」さんの動画では、頻繁に「再現性」という言葉が出てきます。これは、スポーツであれビジネスであれ、成果を出すための本質を突いたキーワードだと感じます。
情報処理モデルの全体像(ビジネスの世界)
前章では、人間や組織の意思決定の流れを「情報の収集・蓄積」「情報処理(判断)」「アクション」の3ステップに分け、それぞれの高度化レベル(レベル1~4)を紹介しました。
今回は、このフレームワークを活用して、実際の業務がどのように情報システムと結びついているかを見ていきます。
受注処理業務に当てはめてみる
たとえば、多くの企業で行われている以下のような受注処理業務を考えてみましょう。
注文(FAX)を受けて → 販売管理システムに入力 → 内容をチェック → 出荷依頼
この一連の流れを、情報処理モデルで分解すると次のようになります。
- 「注文(FAX)→入力」
これは「情報の収集・蓄積」にあたり、レベル2(アナログだが整理済)からレベル3(構造化されたデジタル)への移行作業です。 - 「入力内容のチェック」
これは「情報処理(判断)」に該当し、人による確認作業です。出荷先や出荷数量などが正しいかを判断します。 - 「出荷依頼」
実際の「アクション(処理)」で、指示を出すフェーズです。
情報処理モデルと情報システムの関係
先ほどの「図:情報処理モデルの4レベル分類と3ステップ」との関連で話しましょう。
「注文(FAX)を受けて → それを販売管理システムに入力する」という業務は、情報処理モデルでいうところの「情報の収集・蓄積」にあたり、レベル2(整理された紙情報)からレベル3(デジタル化)への移行作業と位置づけられます。
次に、「入力内容に誤りがないかをチェックする」工程は「情報処理(判断)」に該当し、 「出荷依頼を行う」作業は「アクション(実行)」にあたります。
以下の図をご覧ください。青色で示した部分が、従来の情報システムを活用した業務領域です。 この領域では人が介在することによって、「スピードが遅くなる」「ミスが発生しやすい」といった課題が生じています。
図:情報処理モデルと情報システムの対応関係(青=従来の手作業領域、黄=技術活用領域)
こうした課題を防ぐために、企業では業務マニュアルを整備し、作業のルール化・標準化を図ることで、業務の再現性を担保しようとしています。
たとえば、販売管理システムに入力された内容をチェックする工程も、実際には「元のFAXに間違いがない」前提であれば本来は不要な作業です。つまり、「人が関わること」が、ミスとチェックという“負の連鎖”を生み出しているのです。
デジタル化で業務はもっと楽になる
このような業務も、FAXの情報を自動で取り込めるようにすれば、そもそも「入力ミス」や「チェックの手間」は発生しなくなります。つまり、青い領域を黄色の領域(自動化・AI活用)に置き換えることができれば、業務の精度・スピード・再現性すべてが向上するのです。
このように情報処理モデルを活用することで、「今どの部分が人手依存か」「どこをデジタル化・自動化できるか」が明確になります。
次回は、具体的な業務領域別の活用事例を通して、さらに実践的な内容を紹介していきます。
👉ご相談はこちらまで

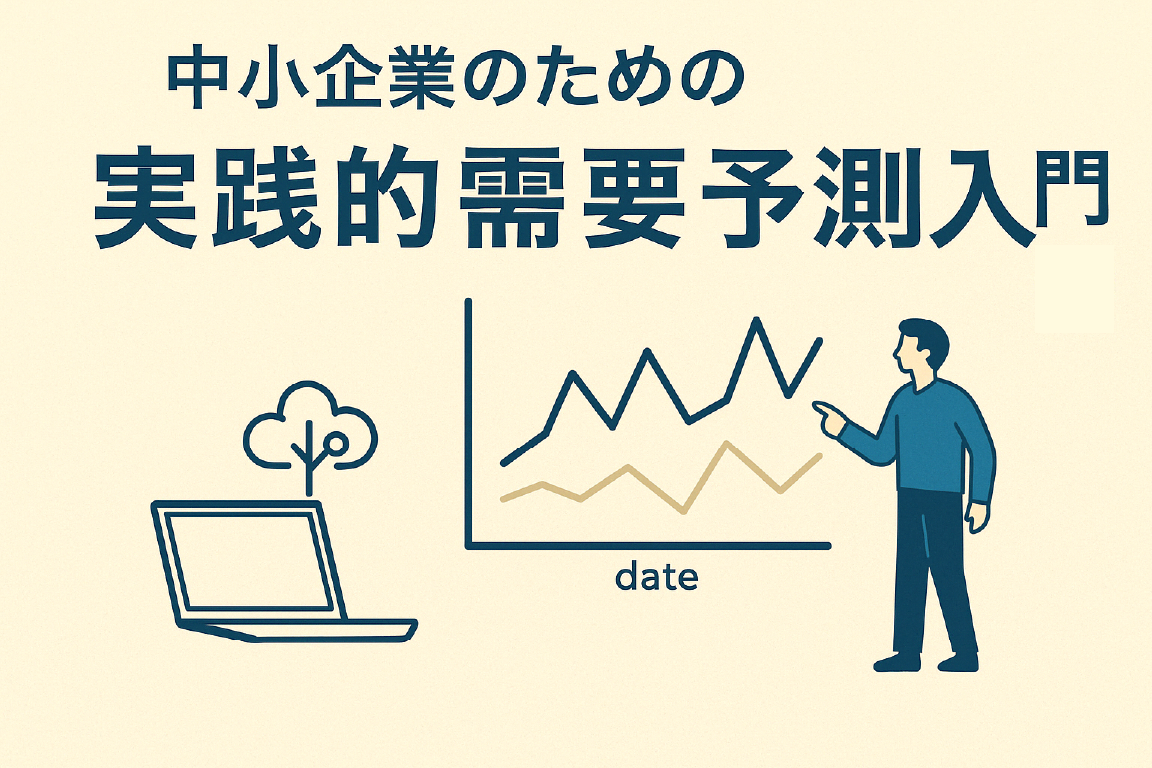
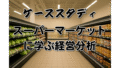
コメント