前回のコラム「財務分析入門①」では、「収益性」「生産性」「安全性」といった財務分析の基本的な指標をご紹介しました。
今回は、ある中小企業の財務データを用いて、実際にどのように分析を進めていくのかをご紹介します。
ケース企業の概要と財務諸表
ケース企業の概要
業種:地域密着型の食品スーパーマーケット
惣菜・日配品・青果・鮮魚・精肉などを幅広く取り扱う
年商:約6.2億円(620百万円)
規模:従業員49人(パート・アルバイト含む)、中規模店舗を郊外に2店舗展開
財務データ(BS/PL)
この企業の直近2期分の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)を見てみます。※単位は百万円
表:直近2期のBS
店舗の改装や設備の更新により、有形固定資産が195百万円まで増加しました。これを借入金で賄っているため、負債も増加しています。
表:直近2期のPL
今期は売上が増加している一方で、営業利益がマイナスに転じ、赤字に陥っていることが分かります。
いったい何が原因なのでしょうか?
各種指標の変化と分析
まずは大まかに、前期からの変化を確認します。
- 売上高は増加:販促や来店客数の増加による
- 売上原価が急増:仕入価格上昇、粗利率低下
- 販管費(特に人件費)が増加:従業員45人 → 49人に増員
以上を踏まえ、より詳細に指標を確認していきます。
収益性分析
売上高総利益率(粗利率)が大幅に悪化(31.0% → 25.8%)
販管費率が高止まり(103%)
→ 結果として、赤字転落につながったと考えられます。
総資本回転率も業界平均を下回る:資産を活かしきれていない兆候です。
生産性分析
労働生産性が大幅に悪化:粗利の減少と付加価値率の低下が主因
労働装備率と有形固定資産回転率が業界平均より低い
→ 設備投資に対して売上・利益が追いついておらず、資産効率の面でも課題が見られます。
安全性分析
当座比率が40%を下回り、資金繰りの悪化が顕在化
売掛金と棚卸資産の増加が現金圧迫の主因
→ 食品スーパーとしては売掛金の存在自体が異例であり、法人向け納品等が考えられます
固定比率が205%超:明確な過剰投資状態
まとめ
このモデル企業は、「売上増」には成功しているものの、「粗利の確保」と「コスト管理」が追いついておらず、典型的な“売上はあるが儲からない企業”に陥っています。
特に以下の点が課題として浮き彫りになっています:
- 粗利益率の悪化による収益性低下
- 人件費の増加と生産性の悪化
- 在庫・売掛の増加によるキャッシュフロー悪化
- 固定資産の過剰投資と資産効率の低さ
これらは財務分析を通じて明らかになった課題ですが、本質的な原因を特定するためには、さらに深掘りが必要です。たとえば、粗利益率が低下している要因は何か?
商品別に見た場合はどうか? 近隣の競合店と比べてどうなのか?――こうした観点で分析を進めることで、真の原因が見えてきます。
また、人件費の増加についても、単に人数が増えたからではなく、「適切な人員配置がされていたか」「労働時間は最適に管理されていたか」といった点まで掘り下げることで、実態が明確になります。
財務分析とは、あくまで経営活動の結果として現れた“数字”です。数字そのものを眺めていても、分かることには限界があります。
重要なのは、その数字がどのような活動の結果として生まれたのかを突き止めることです。
この「活動レベル」まで踏み込んで分析を行うことが、真の改善に繋がる第一歩となることを忘れないでください。

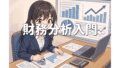
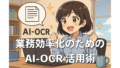
コメント