以前のコラム「ケーススタディ:スーパーマーケットに学ぶ経営診断の実践」で経営診断を行う際には現状分析(内部分析、外部分析)を行うことが重要であると述べさせていただきました。財務分析入門シリーズでは内部分析で行う財務分析を説明していきたいと思います。
今回はその中でも、基本となる収益性、生産性、安全性に関する話をしていきます。
BS(貸借対照表)とPL(損益計算書)
まずはBSとPLの考え方に関して説明をしていきます。
BS(貸借対照表)
貸借対照表は、以下に示すように左側に資産、右側に負債と純資産と記載され
資産=負債+純資産(資本)となります。これは理解している人も多いでしょう。
これに人が何をしているかを加えて、見ていきましょう。
まず右側の負債に関しては誰か(金融機関等)から借金をして借りてきたものになり、いずれ返済する必要があります。一方で、純資産(資本)は投資家が出資したお金であり、基本的には返済する必要はありません。
このようにして調達したお金が右側となります。このお金(資金)は企業活動として、従業員によって運用されていき、資産を生み出していくことになります。
PL(損益計算書)
PLは1年間どのような活動を行ったかを示すもので、売上から費用を引いて利益を計算したもので、以下のような形式となっております。詳しい説明は避けますが、ここでは利益の解釈に関して説明します。
■売上総利益
売上から売上原価(原材料等)を引いたもので、どれだけの商品やサービスを販売してどれだけの利益を得たかを意味しており、「商品・サービスの評価価値」と解釈することが出来ます。
■営業利益
売上総利益から販売費及び一般管理費を引いたもので、事業として見たときに人や設備を使ってどれだけの利益を得たかを意味しており、「事業の評価価値」と解釈することが出来ます。
■経常利益
営業利益から営業外損益(営業外費用-営業外収益)を引いたもので、本業以外の損益を加味した利益を意味しており、「会社の評価価値」と解釈することができます。
※営業外費用は主に支払利息
最後に税金を引いた金額が当期純利益でBSの利益剰余金という所に積み立てられます。
財務分析とは
さて、BSやPLを使って企業の状態を把握していきましょう。
財務分析で分かることは主には以下の5つに集約されるかと思います
(1)収益性分析:利益を上げる力を測る
(2)生産性分析:資産や人・設備をどれだけ効率的に使っているか
(3)安全性分析:借金返済や資金繰りの健全性を評価
(4)成長性分析:将来に向けて伸びているかどうか
(5)キャッシュフロー分析:実際にお金が回っているか(黒字倒産の回避)
上記の指標を算出し、その指標を以下のように見ることで企業の状況が明らかになってきます。
・時系列的にどうなっているのか
・他の企業(同業種、同業態)と比べて、良いのか悪いのか
今回は(1)~(3)に関して話をしていきたいと思います。
収益性分析
収益性分析では、どれだけの元手(資産)からどれだけの利益を得たのかという指標で見ていきます。同じ利益を得るのでも、少ない資産で収益を得た方が良いという考え方です。
これは総資本経常利益率(①)といい、経常利益÷総資本(総資産)で表されます。
この指標は、以下の②、③に分解することが出来ます。
②売上高経常利益率=経常利益÷売上高 →売上に対する利益の高さ
③総資本回転率=売上高÷総資本 →資本がどれだけ有効活用されたか
飲食店に例えると、1000円のランチの利益が500円なら②は50%で高い方が良く、お店の大きさ(席数)を資本と考えたときに、何回転したかが③です。
このようにブレイクダウンしていくと、以下の図のようになります。
④~⑨に関して触れておくと、
④~⑥:これはPL(損益計算書)で説明した利益の捉えかたの違いによるものです。
⑦~⑨:これは日々の経営活動に関係する資産(売上債権、棚卸資産、固定資産)がどれだけ効率的に運用できているかを示すものです。
⑦売上債権回転期間:売上債権÷1日当たりの売上高
回転期間が長いほど、売掛金の回収に時間がかかっていることになり、良くない状況
⑧たな卸資産回転期間:たな卸資産÷1日当たりの売上高
回転期間が長いほど、在庫が長期間滞留しており、良くない状況
⑨固定資産回転期間:固定資産÷1日当たりの売上高
投下された固定資産が効率的に売上に結びついていないため、良くない状況
このように、見ていくことで企業の収益性を把握することが出来ます。
生産性分析
「資産や人・設備をどれだけ効率的に使っているか」という指標で代表的な指標が労働生産性(①)です。これは、人の労働に対してどれだけ付加価値を出しているかというものになります。
この指標を前章同様にブレイクダウンすると以下になります。
付加価値は企業が生み出した成果(売上)のうち、外部から購入した原材料やサービス以外の「内部で生み出した価値」を意味します。幾つか算出方法があるのですが、簡易的には売上総利益(売上高ー売上原価)と思ってください。
労働生産性をブレイクダウンした指標を以下に説明します。
②売上高付加価値率:付加価値÷売上高 → どれだけ売上に対して付加価値を生み出しているか
③一人当たり売上高:売上高÷従業員数
さらにブレイクダウンすると、
④:労働装備率 → 従業員一人当たりの設備を意味し、機械化が進めば高くなります
⑤:有形固定資産回転率 →設備の稼働率
つまり、機械化を進めてその機械の稼働率を高めると一人当たりの売上高は高まります。
このように見ることで、企業の生産性を可視化することが出来ます。
安全性分析
安全性分析とは、企業の財務的な安定性や支払い能力(=倒産しにくさ)を評価する分析手法です。主に「短期の支払能力」や「財務の健全性」に着目して、債務超過や資金ショートのリスクがないかを判断します。
① 流動比率:
「直ぐに返さなくてはならない負債を返せるのか」という観点です。
分母の流動負債に対して、分子の流動資産(現預金、売掛金、たな卸資産など)が十分にあるかを示す比率です。一般的には200%以上が望ましいとされます。
② 当座比率:
流動資産の中でも、たな卸資産などのすぐに現金化しにくいものを除き、現預金・売掛金・有価証券などの即時換金性の高い資産が、流動負債に対して十分にあるかを示す視点です。100%以上が望ましい目安です。
③ 固定比率:
自己資本によってどれだけ固定資産をまかなっているかを見る比率です。
固定資産 ÷ 自己資本で計算され、100%以下が望ましいとされます。
この比率が高すぎると、自己資本では固定資産をまかないきれず、過剰投資や財務の硬直化を招いている可能性があります。
④ 固定長期適合率:
自己資本に加えて長期借入金を含めた「長期安定資金」が、固定資産をしっかりカバーできているかを示す指標です。
固定資産 ÷(自己資本+固定負債)で計算され、100%以下が望ましいとされます。
流動資金を固定資産に充てていないかを見る、より現実的な安全性指標です。
⑤ 自己資本比率:
総資産のうち、どれだけが自己資本(返済不要な資金)で構成されているかを示す比率です。
自己資本 ÷ 総資産で計算され、一般的には30%以上が財務の安定性の目安とされます。
この比率が高いほど、借入に依存しない強固な財務体質と評価されます。
以上が、「収益性」「生産性」「安全性」の財務分析の基本です。
次回は財務分析入門②で実際のケースを例に分析をしてみましょう。


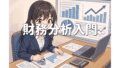
コメント